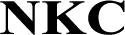介護技能実習のご案内
介護職種の追加の趣旨
平成29年10月16日 現在
介護の技能実習生の受入に当たっての要件(厚生労働省大臣告示に規定)は、平成27年2月4日の提言(外国人介護人材受入の在り方に関する検討会中間まとめ)に沿い設定されています。
詳細や変更がある場合の確認は外国人技能実習機構の介護職種の基準についてでご確認ください。
介護職種の追加は技能実習法に基づく主務省令の改正により定められ、技能実習制度と同様に開発途上地域等への技能等の移転を図り経済発展を担う人材育成から国際協力することになるため、世界規模で高齢化に対して介護ニーズの高度化や多様化に対応している、日本の介護技術を取り入れようとする考えが生まれているようです。
そのため日本の介護技術を世界へと技術移転することは、大いなる国際協力に伴い意義があり趣旨にも適しているということから技能実習制度へと追加されることになりました。
追加との要件について
介護職種および介護作業
外国人介護人材の受入は、介護人材の確保を目的とするのではなく技能移転という制度趣旨に沿って対応。
職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で職種追加。
- 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること
- 外国人について日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること
- 介護のサービスの質を担保するとともに利用者の不安を招かないようにすること
要件1
移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会の仕組み・心と体の仕組み等の理解に裏付けられた以下の業務を移転対象とする。
| 必須業務 | 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等) |
|---|---|
| 関連業務 | 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等) |
| 周辺業務 | その他(お知らせなどの掲示物の管理等) |
要件2
必要なコミュニケーション能力の確保
1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準で「N4」程度、2年目は「N3」程度が要件となり、入国後はOJTや研修等により専門用語や方言等に対応。
| 第1号技能実習(1年目) | 日本語能力試験のN4に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること |
|---|---|
| 第2号技能実習(2年目) | 日本語能力試験のN3に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること |
- 【N3】日常的な場面で使われる日本語をある程度理解しているレベル
- 【N4】基本的な日本語を理解することが可能なレベル
要件3
適切な公的評価システムの構築
- 新制度の技能実習要件を満たす団体の試験実施機関を選定
各年の到達水準は以下になります。
| 1年目 | 指示の下であれば決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル |
|---|---|
| 2年目 | 指示の下であれば利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
| 3年目 | 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
| 5年目 | 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル |
要件4
適切な実習実施機関の対象範囲の設定
- 介護の業務が現に行われている機関を対象(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
- 技能実習生の人権擁護や適切な在留管理の観点から訪問系サービスは対象としない
- 経営が一定程度安定している機関に限定(原則として設立後3年を経過している機関)
要件5
適切な実習体制の確保
| 受入れ人数の上限 | 小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合は常勤職員総数の10%まで |
|---|---|
| 受入れ人数枠の算定基準 | 常勤職員の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定 |
| 技能実習指導員の要件 | 介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等 |
| 技能実習計画書 | 技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める |
| 入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ |
要件6
日本人との同等処遇の担保
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、EPAにおける取組を参考に監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討し以下の方策を講じる。
| 受入時 | 賃金規程等の確認 |
|---|---|
| 受入後 | 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告 |
要件7
監理団体による監理の徹底
技能実習法における一般監理団体の許可(優良要件の認定)を受けていることなど、技能実習制度本体の見直しによる新制度に沿った監理の徹底を図る。